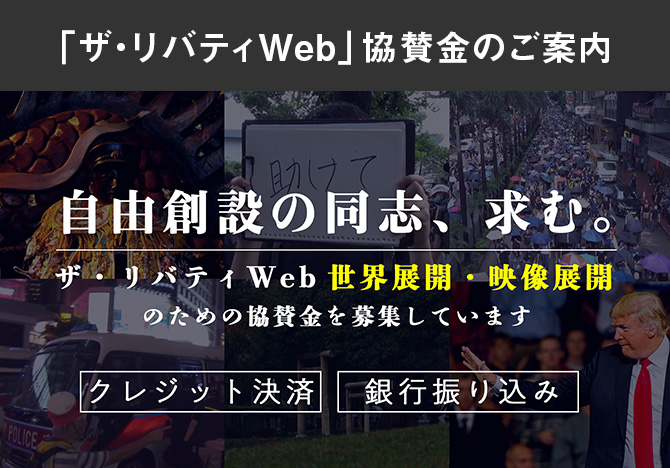《ニュース》
トランプ米大統領が5日からアメリカのすべての輸入品に最低10%の関税を課し、9日より欧州連合など約60カ国には税率を上乗せすると発表したことに、世界が大揺れです。
《詳細》
多くのマスコミは、「かつて輸入品に対する相互関税が導入されたことで、世界恐慌が起きた」という恐怖を煽り、トランプ関税を痛烈に批判しています。その声の大きさにのまれ、「トランプ政権がなぜそのようなことをするのか」という合理的な狙いが完全にかき消され、トランプ氏への非難がとめどなく広がっています。しかし、同氏が一律関税を課すこと自体は前々から発信されており、そこをまず読み解く必要があります。
それを考える上で参考となるのが、同政権のスティーブン・ミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長の41ページからなる論文です。今月末号のリバティ本誌でも詳述しますが、関税強化を訴えるミラン氏の問題認識は、「戦後のアメリカは寛大な低関税で自国の市場を開放する一方、他国は高関税で自らの市場を保護し、アメリカの安全保障の傘も十分に負担していない」という点にあります。
そこで既存の金融秩序の再編を含め、ドル高による経済不均衡を解消すべく、アメリカは各国に関税を課し(今回の関税がこれに該当)、米国債の大量保有などで自国通貨安に持っていく国や、防衛コストを負担しない国などに、さらなる関税を課すよう提起しています。そして関税を「交渉手段」として活用することで、かつて円高・ドル安に誘導した「プラザ合意」のような多国間による通貨調整の案(マールアラーゴ合意)に触れ、「ドル高を是正し、製造業などを復活させる意図」を鮮明にさせているのです。
一方でミラン氏は、手段とはいえ、物価高を招くと指摘されている関税のデメリットについて、大規模な規制緩和や為替の調整(ドル安)、金利の引き下げ、エネルギー価格の下落などの他の政策を組み合わせることで、デメリットを相殺できるといいます。
もちろん、このようなアイデアがすべて実現するかはさておき、いずれにせよ、トランプ政権は、米経済を弱体化させる既存のシステムを見直すと何度も指摘してきたため、従来のレールに乗っかってきた多くの国は、短期的には負担が増える可能性があります(株価については、トランプ氏の経済参謀であるスティーブン・ムーア氏が、第一次政権時から関税を導入して以降も株価は上昇し続けてきたため、一時的に下落しても持ち直すと分析)。
また、感情的に反発する前に、「アメリカがこれ以上弱体化すれば、世界はかえって不安定化し、別の危機がやってくる」ことも冷静に踏まえるべきです。特に今回の関税で最も打撃を受けるのは、アメリカに5000億ドル(約74兆円)相当のモノを輸出している中国です。その中国は9日より「34%という高関税」が課されるため、大反発しています。つまり、中国を弱体化させる米中貿易戦争が一段と激しくなっているのです。
《どう見るか》