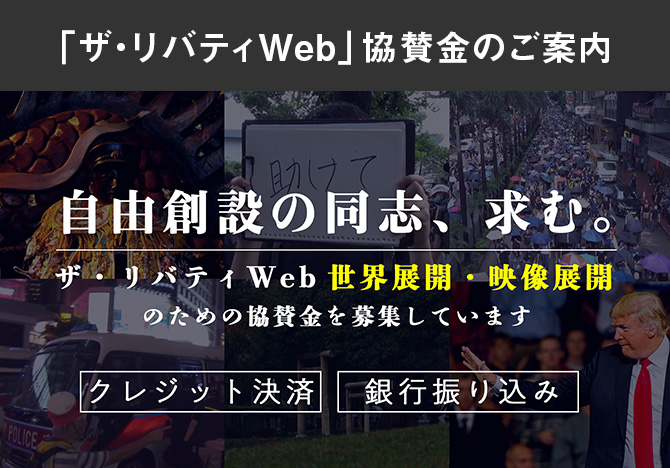《本記事のポイント》
- なぜ「福祉国家」が問題なのか
- MMT理論が危険な理由
- 「福祉国家」の罠にはまらない考え方
もしも「社会福祉政策が充実した国家」と「そうでない国家」のどちらを選びますか、という素朴な質問を投げ掛けられたら、皆さんはどちらを選択しますか。
何事も多数決で物事を決める民主主義国家においては、恐らく多くの人が社会福祉政策の充実した国家の方が良いと答えるのではないでしょうか。
一生涯を通じて安定した生活を国家が保障してくれる、文字通り「ゆりかごから墓場まで」きめ細かく日常生活の面倒を見てくれる国家であるならば、あえて生活リスクを負うよりは、国民は苦労しないで済むというわけです。まさにこの甘いささやきにこそ「福祉国家の罠」が存在していると言えますので、今回はこのテーマを取り上げます。
社会選択の自由が奪われる危険性
いわゆる「北欧モデル」と呼ばれる高福祉・高負担を特徴とする北欧の国家では、国民の公費負担は収入の7割を超えると言います。その分、医療費や教育費は個別に負担しませんし、生活保護費、失業対策費も充実し、生活に困ることはないわけです。
では、この至れり尽くせりの福祉国家の何が問題なのでしょうか。まず言えることは、少なくとも社会福祉政策を充実させるという以上、その財政負担、公費負担は大きくなる訳ですから、必然的に政府機能も大きくなります。
そして政府の関係省庁による政策決定の領域がどんどん増えていきます。すると、国家による配給制のような経済体制になり、民間企業や国民一人ひとりの自由な意思決定による選択肢が制限され、民業を圧迫します。
さらに、本来は自主的な活動であるべき社会的なボランティア活動や各種福祉団体も公費を運用する政府系組織となり、その需要が拡大し、公務員の数が増え続けます。経済活動は、各種規制でがんじがらめになり、個々の民間企業の自由な販売や、価格決定の自由さえ奪われて、経済活動が停滞するようになります。この「一人ひとりの国民や企業の意思決定の自由がどんどん失われていく」というところが危険なポイントです。
収入における公的負担率が増え続け、私有財産形成の自由が徐々に失われていくと具体的にはどうなるのでしょうか。人生の中で創意工夫し、汗水たらして働いて稼いだ収入から、その都度所得税や消費税等の税金を支払い、せっかく蓄えた私有財産でさえ、人生の最後に贈与税や相続税として国家にむしり取られる。それこそ資本主義の精神が傷つき、国民個人の勤労精神も蝕まれ、私有財産の継承権さえ奪われる社会になっていくわけです。
常に豊かになるのは国庫であり、国民一人ひとりはひたすら自由意志で使える私有財産は減り続け、結果平等で貧しくなる。最後は国民の「貧しさの平等」が実現する。公金に群がる既得利権という温床もできます。この流れの中に本質的な問題があるのです。
では、なぜ今その罠に落ち込む危険性が現代の日本にあるかと言えば、議会の少数派に追い込まれた政権与党側が、「目に見えるかたちでばら撒けば票になる」ということで、選挙に勝つために野党側に擦り寄り、選挙公約として誰にでもわかる手厚い社会福祉政策をマニフェストとして掲げたとします。
すると政府批判をする野党の出る幕はなくなるので、本来は国民の血税による負担でもあるにもかかわらず各種政策を無償化と呼び、常にバラマキ政策のメニューが並び、選挙後に財政負担が増大してより大きな政府になり、結果的に大増税という形で国民への大きな負担になって返ってくることになるのです。
政権与党にとっては耳の痛い話でしょうが、これをもって選挙の度に行われる有権者に対する合法的買収に当たるという見解はあながち間違っていないと思います。「地獄への道は善意で舗装されている」とはよく言ったもので、ここにも福祉国家の罠があると言っても過言ではないでしょう。
何事も「過ぎたれば及ばざるが如し」です。この国家による行き過ぎた公費の支出、徴税権の濫用とも言える状況に対して、はっきり国民の側からノーを突きつける必要性は日に日に増しているとも言えるでしょう。
おそらく、財政負担の大きな政府によって提供される手厚く生活を保護する社会に慣れてしまえば、あえてリスクを背負って果敢にチャレンジしていく価値を疎い、多くの国民が「次に政府は何をしてくれるのか」ばかりを考え、常に政府に対して依存し、従属的になり、社会変革への意欲を失い新たな価値を生み出すイノベーションが社会から奪われて、国家そのものが衰退していくことはほぼ間違いないでしょう。
この自助努力で自らの人生の可能性を広げて、掴み取っていくチャンスが奪われていく社会こそ、福祉国家の罠とは言えないでしょうか。
MMT理論も要注意
その意味で、ここで注意しておきたいのは、最近話題となっている日本全国での「財務省解体デモ」を支援するような形で、国民の公的負担を減らすという趣旨で再び脚光を浴びているMMT理論も、自国通貨発行権を持つ国家が発行する国債は、原則として極端なインフレにならない限りいくらでも発行できるという考え方を基本としています。
ですから、政府による積極的な財政出動を前提としているという意味で、財政赤字もなんのその必然的に国債発行により国家財政がどんどん大きな政府になっていきますので要注意です。
インフレ率を適正にコントロールできるかも未知数ですし、国債利払い負担がどんどん増大していきます。何よりも国家に依存する国民が政策決定プロセスを無批判に受け入れてしまい、国家の財政規律に対してチェック機能が働かずに、結果的に国民経済に深刻な悪影響を与える可能性が出てきます。
自助の精神で繁栄する社会構築へ
かつて英国サッチャー首相は、大きく衰退した英国経済において、単なる自営業の促進に留まらず、国家からの自立と自己責任を重視する思想的スローガンとして「セルフ・エンプロイド」という自助の精神に基づくスローガンを提唱して、英国経済を見事に復活させました。税金と社会保障費を合わせた国民負担率がすでに5割に及ぼうとする現在の日本は、まさにそのサッチャー首相登場前の英国の危機に近い状況に陥ろうとしているとも言えます。
社会的弱者へのセイフティネットとして必要不可欠な行政サービスは政府が担うことがあったとしても、それ以外の社会福祉政策においては、企業単位での福利厚生の一環として出来る制度は拡充出来ないのか、地域コミュティの相互扶助の中で出来ることはないのか、核家族ではない三世代通じた家族の扶助で出来ることはないのか等々を考える。
すなわち国家による行政サービスに頼り切る前に、今こそ国民一人ひとりが「いま自分から出来ることはないか」を真剣に考え、智慧を出し合って、自助の精神で築き上げる社会を考えてみる必要があると思います。
その上で、財政負担の少ない効率の良い小さな政府の下で、失敗を恐れずに果敢にリスクを取り、次世代の日本の繁栄を築くために、新たな事業創造にチャレンジしていくような創造的起業家を次々に養成することが肝要ではないでしょうか。
現代の政治は、国民に対し、「どこまで公費負担に耐えられるのか」を試す「耐久テスト」を行っています。そうした政治と訣別し、くれぐれも自国民を隷属させ選択肢を与えない「不自由な福祉国家の罠」にはまらないように注意いたしましょう。
(吉崎富士夫)
【関連書籍】

『経営者マインドの秘密』
大川隆法著 幸福の科学出版
【関連記事】
2025年3月号 もらってばかりの人生は駄目! バラマキ亡国論 ──『なお、一歩を進める』の読み方(2) - Part 1 究極のすねかじり男 マルクスの呆れた生涯
https://the-liberty.com/article/21925/
2024年2月号 日本のガラパゴス保守 - Part 2 大きな政府を広げる「エセ保守」に要注意!