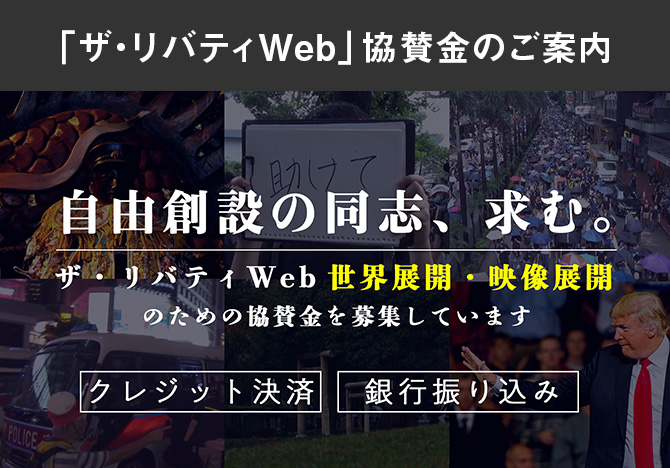本誌7月号記事「10年後のあなたをつくる 大川総裁の勉強術」では、大川隆法・幸福の科学総裁がさまざまな著作・法話で説いてきた、王道かつ智慧に満ちた勉強法を紹介した。本欄では、そこでは盛り込み切れなかったポイントに光を当てる。自分の勉強スタイルをつくっていく、新しい視点が得られれば幸いだ。
今回は、大川総裁の"二刀流読書術"について。
「精読」と「多読」を併行させる思わぬ効果
大川総裁は、企業が人材を採用する時、実用の学(実務訓練)を修めている人が「即戦力」として重宝されがちである一方で、それだけでは人材が管理職に化けていくかといったポテンシャは読み切れないと語る。
そのポテンシャルをチェックする点の一つが「その人が、手先でできる仕事以外に、教養のために払う時間を持っているか。努力した形跡があるか」。それが「人を使える力」に変わってくるというのだ(『仕事ができるとはどういうことなのか』)。
現に大手メーカーなどでは技術系出身の人が多いものの、理科系で優秀な人が名門学校から入ってきても、せいぜい技術部長くらいまでしか行けない人が多い。そこを抜けて上がってくるタイプの人というのは、理系の専門以外に、歴史や政治、経済、小説といった幅広い教養を身につけてきたタイプだと、大川総裁は指摘する。この部分が総合的な判断能力の裏支えになるためだ(『夢は叶う』)。