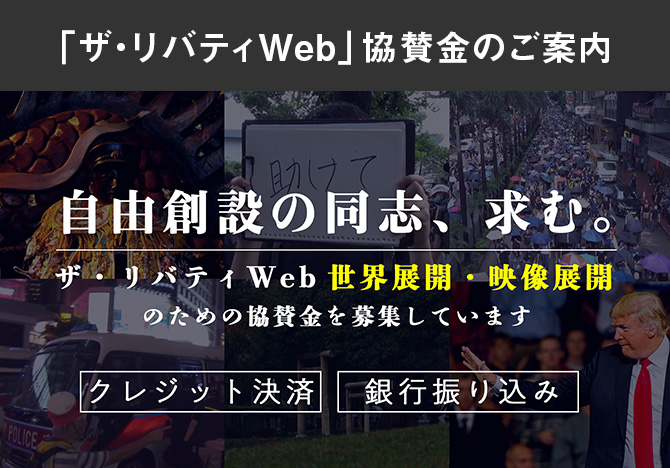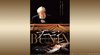みなさん、こんにちは。5月23日、幸福の科学のアニメーション映画『ドラゴン・ハート─霊界探訪記─』が劇場公開されます。同作の原作ストーリーは大川隆法総裁が、あの世の芥川龍之介の霊からインスピレーションを受けて綴ったものです。今回はそれに関連して、芥川作品を映画化した世界的名作『羅生門』を取り上げます。
黒澤明が1950年に撮った本作は、ヴェネチア映画祭金獅子賞や米アカデミー特別賞を受賞し、敗戦後5年目という時期において日本映画の水準の高さを世界に知らしめました。その金字塔が芥川と黒澤という二大芸術家のコラボであることも意義深いですが、さらに驚くべきは、本作が幸福の科学的にいえば"霊言映画"であることです。
平安時代、盗賊・多襄丸が旅の侍夫婦を襲い、女を手込めにして夫を殺す。彼は捕らえられ裁判となるが、当事者三人の証言がすべて食い違う。三人とは多襄丸、女、そして巫女の口を通して語る、殺された侍の霊である──。
上記は芥川の短編「藪の中」の通りですが、脚本はそこに彼の短編「羅生門」を、ストーリーの外枠を囲む額縁のように組み込み、巧みな映画的語り口を生み出しています。
原作「藪の中」も当事者と関係者の証言だけで成り立っており、何が客観的真実なのかは書かれていません。それを通常の作品鑑賞では「三人のうち二人が嘘を言っており、人間の弱さや醜さ、手前勝手なエゴイズムが描かれている」と解釈するわけですが、仏法真理的にはもっと霊的な捉え方も可能です。すなわち「出来事は一定不変のものではなく、見る者の解釈によって、その意味付けが、いかようにも変化する」ということです。
特に霊界においては、まさにその通りです。霊界は主観的な世界であり、観る人によって同じ女性が絶世の美女に見えたり恐ろしい魔女に見えたりします(『ドラゴン・ハート』にも似た場面があります)。芥川霊は大川隆法総裁の最新刊『映画「ドラゴン・ハート─霊界探訪記─」原作集』のなかで、こう語っています。
「(霊界では)その人がいちばん『リアリティー』を感じる(中略)世界観を見ることになるね」
この世=三次元世界も霊界の一部なので、そうしたあり方は、この世においてもある程度、成り立っています。芥川は世界のそんな霊的実相を深く感得していたからこそ「藪の中」を書けたのではないでしょうか。芥川霊は同書のなかで、生前から河童などの霊的存在が目に見えていたとも語っています。
この「霊的」ということは映画「羅生門」についても言えます。本作では名カメラマン・宮川一夫の撮影の素晴らしさが有名ですが、昭和の映画評論家、故・淀川長治氏はその点を「『羅生門』はキャメラが映画の霊に乗り移っていた」と、いみじくも「霊」という言葉で評しています(『キネマ旬報セレクション 黒澤明』)。こうなるとこの映画は、脚本・演出・撮影にわたって芥川霊がインスピレーションを与えていたのかもしれないと想像したくなります。そうした強い霊的バイブレーションを帯びているからこそ、世界で高く評価され、多くの映画監督に影響を与え続けているのでしょう。
ここで一つエピソードを。私は昨秋、仕事で、とある温泉街に行き、仕事のあとはその街で友人がマスターをしている飲食店で過ごしていました。すると中年の白人男性の観光客二人連れが入ってきたので、友人と英語で話しかけてみるとフィンランド人とのこと。あなたたちの国では日本の何が知られているかと聞くと、彼らは日本のメーカーや技術の優秀さを挙げ、一人が言いました。「…andクロサワ」。日本人として海外の人たちと文化交流するうえでは、やはり自国の文化の雄である黒澤の主な作品を観ていなければ話にならないと思ったことでした。
映画の終盤、黒澤はあるエピソードを加えています。羅生門で雨宿りをする旅の僧侶は、裁判で三人の証言を聞き、人間不信に陥りかけていたのですが、そこで原作にはない温かい出来事が起き、その僧侶にこう言わせているのです。
「私は人を信じる。私はこの世の中を地獄にしたくはない」
人々が互いに自己中心的な世界観で生きているだけでは、この世の中は地獄になってしまう。しかし、それは「信じる力」によって乗り越えることができる。黒澤は芥川の深遠な文学を消化したうえで、自分が信じるヒューマニズムを述べ、ポジティブな世界に向けて作品を解き放っています。映画の最後で降りしきっていた雨が上がるように、私たちの心にも人間性を信じる希望の光が射してきます。それもまた、本作が名作であるゆえんでしょう。
(田中 司)
『羅生門』
- 【スタッフ】
- 監督:黒澤明 脚本:橋本忍・黒澤明 撮影:宮川一夫
- 【キャスト】
- 出演:三船敏郎 京マチ子 森雅之 志村喬ほか
- 【その他】
- 1950年製作 | 88分 | 大映京都
DVDや各種映像配信で視聴できます。
【関連書籍】