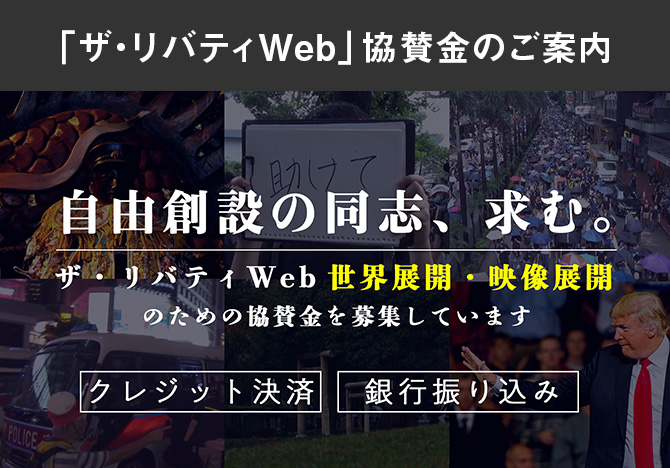《ニュース》
日本維新の会や立憲民主党が7月の参議院選挙の公約に盛り込む「食料品の消費税ゼロ」が、物議を醸しています。
《詳細》
近年、食料品やガソリンなどさまざまなモノの値段が高騰しており、物価高対策として「消費減税」を求める国民の声が相次いでいます。
そうした中、日本維新の会の吉村洋文代表は4月、トランプ米政権の関税政策による物価高騰への経済対策として、「2年限定で食料品の消費税をゼロにすべき」と提言。立憲民主党の野田佳彦代表も同月に、「食料品の消費税率を、原則1年間に限ってゼロ%に引き下げる」案を参院選の公約に盛り込む考えを示しました。
これらの減税案をめぐっては、「一時的な減税では意味がない」「食料品だけでなく、一律で引き下げるべき」「選挙対策に過ぎない」など、多くの批判や不満の声も上がっています。
とはいえ「減税しないよりはマシ」との見方が象徴するように、物価高に苦しむ国民にとってはありがたい政策にも思えます。ただ、「食料品の消費税がゼロになれば、その減税分(8%)の物価が下がる」と考えがちですが、そうはならないという見方が支配的です。減税分を、必ずしもすべて価格に反映させることができないからです。
特に不安視されているのが、「食料品の消費減税は、飲食店にとっては実質的な増税になりかねない」という点です。
レストランなどの飲食店には、「売上の際に顧客から受け取った消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いた差額を納税する」という「仕入税額控除」が適用されています。しかし、食料品が「非課税」になった場合、食材を仕入れる際には課税されなくなりますが、売上にはこれまで通り消費税10%が課されます。そのため、仕入税額控除が効かなくなり(差し引ける金額がゼロになる)、実質的な税負担が増加することになるのです。
この時、仕入事業者が減税分を丸々値下げに回せば、税負担分は相殺されますが、価格を引き下げるかは事業者の判断によります(つまり、義務ではない)。特に、生鮮食品など食料品の多くは、季節や天候などの影響を受けやすく変動も激しいため、容易に引き下げられるわけではありません。「消費減税分だけ値上げして、商品価格を据え置く」という判断をする可能性も十分に考えられます。
こうして仕入価格を下げられず、結果として税負担分を価格転嫁できなければ、とりわけ中小零細の飲食店は資金繰りが厳しくなり、経営に深刻な影響を及ぼします。一部の外食店はすでに、「飲食業界が狙い撃ちされているような形で、すごく腹立たしい気分」など、戸惑いを感じているといいます(5月7日付静岡朝日テレビ)。
《どう見るか》