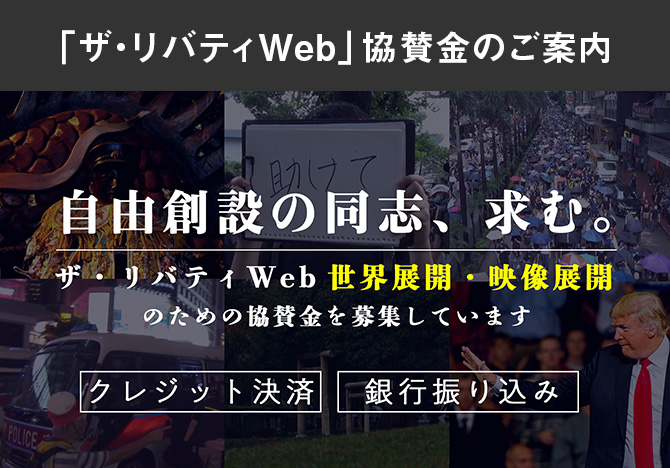「日本人の心の精髄を優れた感受性で表現する、その物語の巧みさ」──。
1968年、川端康成(1899~1972年)は日本人として初めてノーベル文学賞を受賞したが、これがアカデミーが発表した授賞理由であった。
本誌7月号「川端康成が咲かせた『泥中の花』」では、両親と死に別れ、育ててくれた祖父母が死んだ後、孤独の中で作家を志した文豪の人生と、その世界観の一端を紹介した。
本欄のアナザーストーリーでは、異なる角度から、川端の創作世界の根底に流れる価値観について探ってみたい。
「日本の美の伝統のために生きようと考えた」後半生
1899(明治32)年に生まれた川端は、恵まれない家庭環境から旧制一高に進学し、東大を卒業後、文学者として身を立てていく。
しかし、46歳の頃、日本が敗戦し、大きな衝撃を受ける。自分を取り巻く社会が崩壊し、自身の人生もまた、一旦、終わってしまったかのように感じた。
「日本が降伏すると、私は自分をもう死んだものとして感じた。これから後は言わば残生だと思うことによって、私は多くのものを捨てようとした」(「天授の子」)
戦争で友人や知人を失い、先輩の文学者も数多く死んでいった。戦争中は東京新聞で、兵士の遺文を読んで感想を書く連載記事を引き受けており、特攻隊員など数多くの遺文に触れていた。若い頃に両親・祖父母を亡くした川端は、再び多くの死に向かい合うことを余儀なくされ、自分はなぜ生き残っているのかを考えざるを得なかった。
「三十五年以上も前に肉親みなに先立たれてもいる私は、不思議と生き残っている」(「天授の子」)
川端は、空襲が続く最中、夜番をしていた頃、鎌倉の小山で月を眺めた時の記憶を、後に随筆につづっている。
「人工の明りをまったく失って、私は昔の人が月光に感じたものを思った。鎌倉では古い松の並木が最も月かげをつくった。燈火がないと夜はなにか声を持つようだった。空襲のための見廻りの私は夜寒の道に立ちどまって、自分のかなしみと日本のかなしみとのとけあうのを感じた。古い日本が私を流れて通った。私は生きなければならないと涙が出た。自分が死ねばほろびる美があるように思った。私の生命は自分一人のものではない。日本の美の伝統のために生きようと考えた」(「天授の子」)
「永遠なるもの、普遍的なるもの」を追い求める心が、創作活動の原動力であった
戦後、川端は、「雪国」を完成させ、「山の音」や「千羽鶴」、「みづうみ」等の作品を公表する傍ら、日本ペンクラブの会長を務め、次世代の作家を育ててゆく。
小説家として大成し、1968年にノーベル文学賞を受賞するが、その胸中から、「日本の美の伝統のために生きよう」という思いが離れることはなかったようだ。
それは、有名なノーベル文学賞受賞講演「美しい日本の私」にも見て取れる。
悟りを求める心である「菩提心」を月になぞらえて和歌を詠んだ、鎌倉時代の僧・明恵上人の境地について、「月を見る我(明恵上人)が月になり、我に見られる月が我になり(中略)暁前の暗い禅堂に座って思索する僧の『澄める心』の光りを、有明けの月は月自身の光りと思うだろう」と述べている。
明恵上人に仮託して、自身の心情を語っているかのようだ。
煌々と輝く満月──その美を感じ取る心の中の仏性──その二つは離れることはない。かつて心に刻んだ決意を思い起こすかのように、川端は古人に想いを馳せながら、美について語り続けてゆく。
大川隆法・幸福の科学総裁による川端康成の霊言でも明かされていたように、「永遠なるもの、普遍的なるもの」を追い求める心が、創作活動の原動力であった。そうした崇高な理想があったからこそ、ノーベル文学賞の受賞は、戦後の日本人を勇気づけることになったのだろう。
「人間は何度も死にかわり生れかわり、お互いに父や母になり合うもの」
こうして見てくると、川端の成功は、他の文学者のそれとは一味違ったものだったことが分かる。
自分の生命は自分一人のためのものではない。自分の創作活動は、自分一人の美学を表現するためのものではない。日本の歴史につらなる偉人たちが守り続けてきた「美の伝統」を後代に伝えてゆくためのものである──。
そうした境地に到達できたのは、やはり、「目に見えないもの」を信じていたからだろう。本誌7月号の記事でも紹介したように、その奥には、仏教的な価値観が流れている。
二歳になるまでに父母を失い、七歳で祖母、十歳で姉、十四歳で祖父を失った川端は、「葬式の名人」と言われるほど身内の死を経験する。自身も幾度なく病気を経験する中で、人間の生と死に想いを馳せざるにはいられなかった。
その中で、輪廻転生が、「これまでの人類が持った思想のうちでは、最も美しいものの一つだ」と考えるようになる。
幼少期の壮絶な体験からか、作品の登場人物の台詞の中には、親子の縁を説いた『心地観経』の一節が現れている。
「人間というものは何度も死にかわり生れかわりするうちには、皆がお互いに父や母になり合うものです」(「海の火祭」)