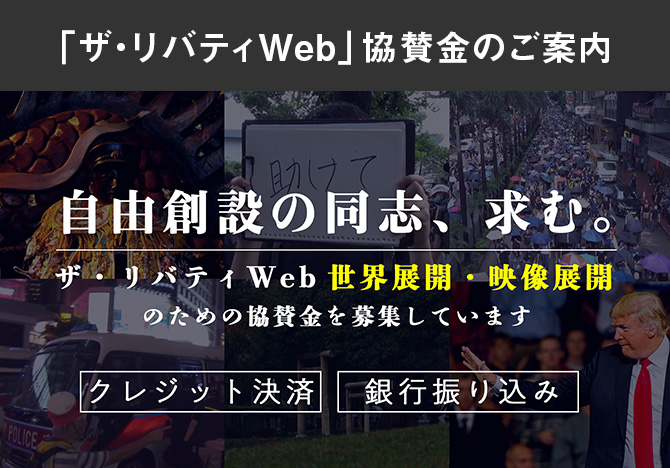29日午前6時45分頃、尖閣諸島の領有権を主張する台湾の活動家2人が乗っていると見られる漁船が、同諸島沖の日本の接続水域(領海の外側約22キロ)内を航行しているところを海上保安本部の巡視船が確認した。
この漁船には少なくとも5人が乗っており、巡視船に接近するなどの威嚇行為は特になく、約4時間半後に同水域を離れた。東日本大震災後、日本に対するこうした行為は国際的な批判の的になると見たためか、沖縄・尖閣諸島沖で中国政府の公船などは一度も確認されていなかった。今回確認された台湾の活動家は、今年1月に発足した台湾、中国、香港の民間団体からなる「世界華人保釣連盟」の幹部と見られている(30日付産経新聞)。
中国漁船による巡視船衝突事件が起きたのは昨年9月。震災からおよそ3カ月が経ち、活動を「自粛」していた中国船の姿が今後、再び増えてくる可能性は高いだろう。南シナ海でのベトナムとの対立など、なりふり構わず海洋権益を狙う中国の動きは一層、強硬さを増しているからだ。
まさに弱り目に祟り目だが、もとはと言えば昨年9月に象徴されるような、領有権を巡る政府の弱腰の対応が自ら危機を招き入れている。普天間基地移設問題についても、いまだに地元沖縄に対する政府からの本腰を入れた説得はなく、日米安保をはじめとする国防政策から逃げ続けているかに見える。
30日付読売新聞に掲載されている世論調査結果によると、「菅直人首相の続投によって政治空白が生じている」とする回答は66.3%に達したというが、日本はこれ以上、政権能力のない政府の元で無為な時間を過ごすことはできない。国防問題をはじめ、原発稼動停止による今夏の電力不足、遅々として進まない被災地復興、採決が見えない今年度予算の赤字国債法案など、これら政治の停滞は国防、経済の両面からさらなる国難を呼ぶことになるだろう。それを回避するための第一歩が、菅直人首相の辞任であるのは論を待たない。(雅)