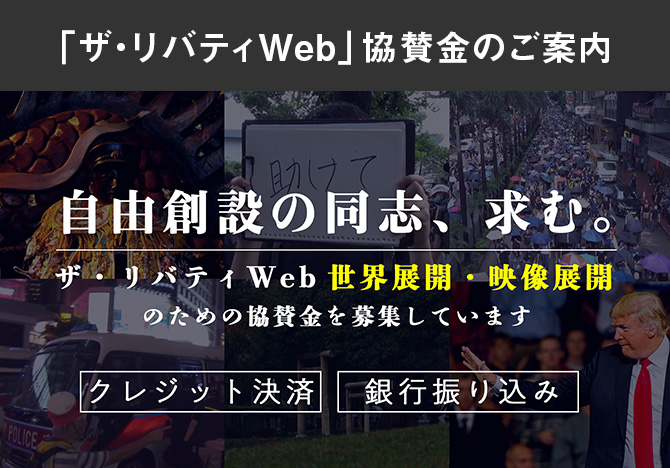《ニュース》
厚生労働省とこども家庭庁の有識者検討会が、出産費用への公的医療保険の適用に向けての初会合を行いました。少子化対策の一環として、出産の無償化を維持するための施策となっていますが、「産院の不足が加速する」との懸念の声も上がっています。
《詳細》
出産費用の公的医療保険の適用は、岸田政権の「異次元の少子化対策」の一環として、2023年6月に発表されたこども未来戦略に明記されているものです。普通分娩による出産を公的保険適用とし、かつ1~3割の自己負担を求めない方向で制度設計を目指しています。
健康保険から支給される出産一時金は1994年に「30万円」で開始されました。しかし、出産費用の上昇に合わせて増え続け、2023年には42万円から50万円へと引き上げられています。ただ、出産費用は施設ごとに異なり、地域間の差も激しいため、東京では正常分娩の費用が約60万円となるなど、無料にならないケースが出ています。
出産一時金の引き上げに合わせて、出産費用を上げる施設が増えていることから、保険適用とすることで全国一律の公定価格を設定し、「便乗値上げ」を防止する狙いもあると報じられています。検討会に出席した女性委員の一人は「全ての人が安心して生むことができる場所が近くにあり、かつ負担も少なくするという両輪をどう実現するか」と発言しています。
ただし、公的医療保険が適用されると出産費用は公定価格となり、医療機関が値決めを行えなくなります。もし、現在の費用よりも公定価格が低くなった場合、お産を取りやめる医院が続出すると危惧されています。既に少子化の影響で分娩数が減少する中でも、24時間体制で分娩を扱う場合に必要なスタッフ数は変わらないため、赤字に陥る医院も出てきている状況にあるためです。
《どう見るか》