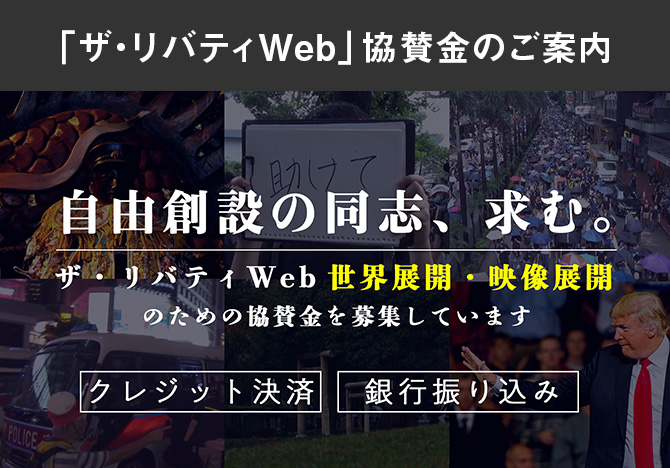2024年7月号記事
川端康成が咲かせた「泥中の花」
日本人で初めてノーベル文学賞を受賞した文豪の、知られざる素顔に迫る。
大川隆法・幸福の科学総裁は、この世の苦しみの中に悟りを発見する「泥中の花」のような人生を生きた人物として、小説家の川端康成(1899~1972年)を挙げている(*1)。
川端は成人するまでに「葬式の名人」といわれるほど身内の死に直面したが、それでも旧制一高(東大の前身)に行き、小説家となり、日本初のノーベル文学賞を受賞した。そうした厳しい環境から、どのように身を起こし、小説家として成功していったのだろうか。
その過程については、さまざまな研究がなされてきたが、いまだにその真相はつかみ切れていない。
(*1)大川隆法著『自も他も生かす人生』(幸福の科学出版)
永遠なるもの、普遍的なるものを求める
この問題について、大川総裁が収録した川端康成の霊言では、本人の心情が赤裸々に明かされている。
「永遠なるもの、普遍的なるものを(中略)追い求めて、それを書き記したいとかね、後世に遺したいとかね、そういうふうに思ってるような人は、それは、神様に近づいていくのさ」(*2)
しかし、それを求めず、「どう生きようと勝手だ」「今日だけ自由であればいい」という人は、「永劫の苦しみのなかに」沈んでゆくという。
文芸の世界では「自由」が賛美されるが、実際は「『自由論』が『堕落論』と一緒」になってしまうことも多い。
「泥中の花」を咲かせるための手がかりが語られていた霊言を軸に、本欄では生前の著作も踏まえ、川端が目指した世界を探ってみたい。
(*2)大川隆法著『文豪たちの明暗』(幸福の科学出版)
霊言で明かされた『伊豆の踊子』作者の意図
川端文学の背景にある価値観
霊界との"交流"を語る文学者