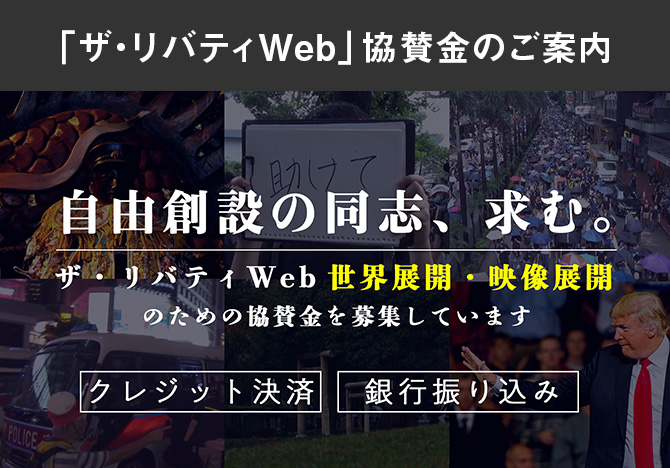兵庫県神戸市教育委員会がこのほど、古代の幹線道路の中継施設「駅家(うまや)」があったとされる同市東灘区の深江北町遺跡から、「智識(在家信者からの寄付のこと)」という文字や「天平」という元号が書かれた奈良時代の木簡が見つかったと発表した。同遺跡では26点の木簡の他に土器やすずりなどが多数出土している。
今回、内容が発表された木簡は、二つに分かれた断片の表に、堂塔や仏像などの建立に金品を寄進することを意味する「智識」のほか、僧侶を指す「咒願師(じゅがんし)」や「朝臣(あそん)」「亀」の文字があり、裏面には「天平十九年八月一日」と読める文字、「廣足(ひろたり)二文」「十文」など、寄付者の名前とみられる文字も並んでいるという。
都以外の地方で仏教に関わる寄進を裏付ける木簡の出土は全国初だということで、奈良・東大寺の大仏建立のため、全国で寄付が行われていた時期と一致しており、市教委は「駅家の役人が集まった寄付金を記録した文書」ではないかと見ている。
各紙によれば、奈良文化財研究所史料研究室は、「庶民から資金を集めたことを具体的に示した初の木簡資料。駅家のような役所が担当していたのは意外で、地方での仏教活動の状況が鮮明にわかる」「『銭一文』という記述もあり、額は少なく、役人が大仏鋳造のため庶民から強制的に寄付を集めたリストかもしれない」と分析している。
東大寺の大仏建立は、聖武天皇の悲願であったが、膨大な資金や多くの人材を集めるため、当時、全国で橋を架けたり池を造るなどのインフラ整備で実績を上げ、民衆の圧倒的な支持を集めていた行基(ぎょうき)を勧進役に抜擢したところ、建立事業は一気に進んだという。
大仏建立やエジプトのピラミッド建設などの大きな事業では、「庶民を奴隷状態で働かせたり、資金を強制的に徴収した」というのが通説であったが、宗教施設の建設に関しては、現代人が失ってしまった強い信仰心を持った人々の「布施の精神」が発揮されたと考えられる。この「寄進リスト」の発見は、そのことをも裏付ける重要な証拠だろう。(宮)
【関連記事】
2005年12月号記事 行基、夢窓疎石、蓮如に学ぶ「国を動かす力」
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=297
2011年9月号記事 世界に誇るすごい日本史─奇跡の日本史 第2部