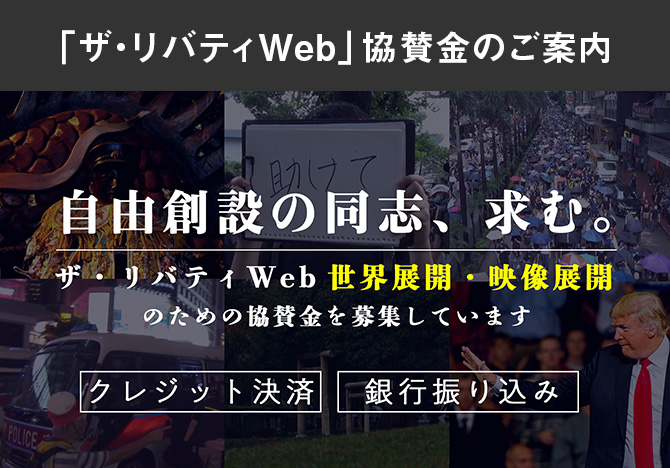米カーネギー国際平和財団は3日、2030年までを見据え、中国の軍事的な台頭が日米同盟に与える影響を分析したレポートを発表した。このプロジェクトには、マイケル・スウェイン上級研究員ら専門家9人が取り組み、約5年をかけて完成させた。
レポートは中国が今後もハイペースで軍拡を続け、軍事力を背景にした影響力を駆使して、日本との外交問題を高圧的に解決しようとすると分析。中国と日米同盟との軍事バランスは変化し、「最も可能性の高いシナリオとして、日米同盟は日本周辺の空や海で軍事的な優位をかろうじて維持するか、軍事バランスが不明確になる」と論じている。
スウェイン上級研究員は、米ニューヨーク・タイムズ紙の取材に「過去60年間維持してきた優位を、アメリカが維持できるだろうか。アメリカはできると言っているが、本当にそうかは定かでない」と、米中の力関係が変化する可能性に言及している(2日付同紙)。
2030年までの長期予想といえば、米国家情報会議(NIC)が昨年末、「グローバル・トレンド2030」という報告書を示している。同文書は東アジアについて、経済面では中国との結びつきを強めるが、防衛分野ではアメリカや周辺国との協力関係を強化しようとするという、二つの流れが起きるという見通しを盛り込んだ。東アジアでの米中による綱の引き合いは、今後も強くなるということである。
アメリカからの覇権交代をもくろむ中国への警戒感は強くなる一方だ。中国はこのほど発表した2012年版の国防白書の中で、これまで核戦略の柱に据えてきた「核兵器の先制不使用」に言及しなかった。中国は、同白書を初めて発表した1998年からこの原則を強調してきたこともあり、同国がより積極的な核戦略を取るように、書き方を改めたのではないかという憶測を呼んでいる。
対するアメリカは、ベビーブーム世代の引退期を迎え、財政問題が長期的に見て今後も悪化する可能性が高い。そこにオバマ政権の福祉バラマキ路線が拍車をかけ、国防費削減路線がすでに始まっている。このままでは、二つのレポートが指標とする2030年を待たずに、アメリカの退潮が決定的になる可能性も捨てきれない。
アメリカの庇護のもとで戦後の繁栄を謳歌してきた日本にとっては、「自分の国は自分で守る」という国防の原則に立ち返らざるを得ない。アメリカの優位が揺らげば、日本が新たな中華帝国に呑みこまれるというシナリオも、絵空事ではないのだ。
【関連記事】
2010年11月号記事 201X年 日本再占領!?